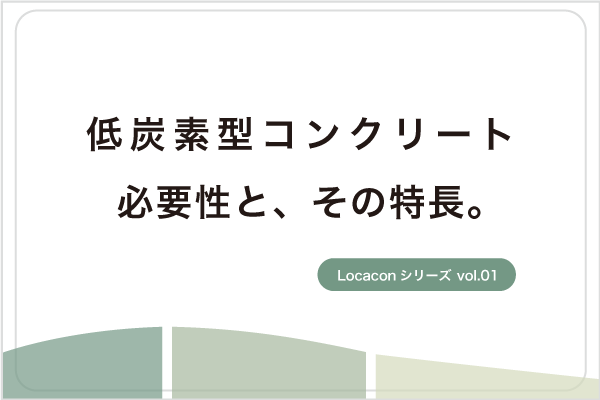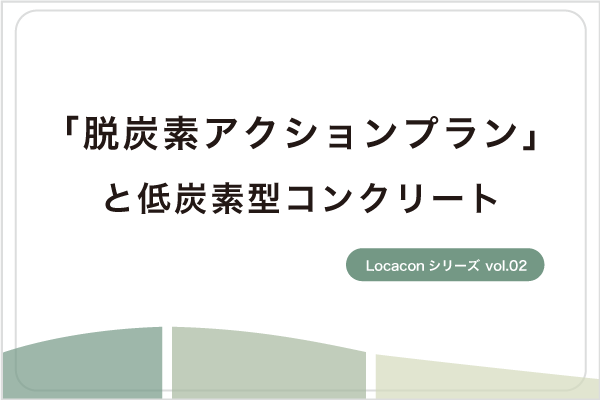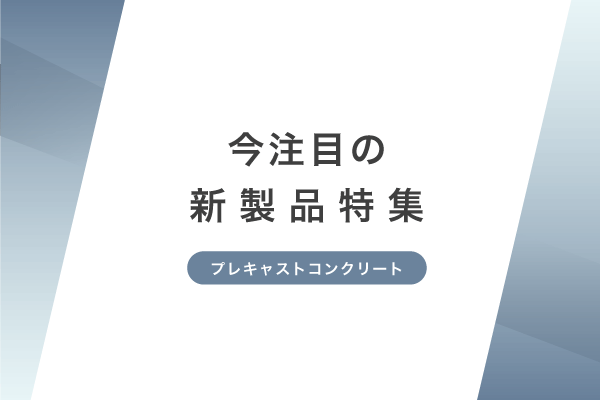第29回 水シンポジウム in やまなし
2025年10月24日に山梨県で水シンポジウムが開催されました。
このイベントは、毎年全国の都道府県で開かれているイベントで、土木学会の水工学委員会や国土交通省などが主催しています。
市民の皆さん、学会、行政、企業などが集まり、水に関するさまざまな課題について理解を深めたり情報を交換したりする場となっています。
当社はブース出展・ポスター展示を行い、浸透貯留槽についてPRを行いました!

ブース展示
ブース展示は当社を含め6社が出展しており、治水・利水に関わる様々な展示が行われました。
当社は貯留・浸透のコンクリート製品、プラスチック製品を展示・紹介しました。
廊下にもポスター展示を行いました。

手前の黒い箱は、プラスチック浸透槽「ニュープラくん」の実物です!
実際にお手に取って頂いたことで、軽さやその施工性を実感して頂けました。

浸透・貯留関係の他にも、低炭素型コンクリート「Locacon」をご紹介しました。「環境にやさしいコンクリートもあるのは知らなかった」「今後は、こうした工法の重要性がますます高まってきますね」といったお声を頂けました!


多くの方にご来訪頂きました。ありがとうございました。
治水と利水
今回のシンポジウムのメインテーマは「山梨・暴れ川富士川の治水・利水・環境 古の知恵と現代の技術の融合 〜過去は未来のみちしるべ〜」でした。富士川とその支流は、3000メートル級の南アルプスから流れ下る非常に急流な河川で、古くから水害に悩まされてきた歴史があります。
武田信玄が、甲府盆地を水害から守るため築いたとされる信玄堤や万力林などの霞堤や水害防備林など独自の治水工法が施されてきました。
国指定文化財|史跡 御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出)
特に注目されていたのが「桝形堤防」と「将棋頭」です。
山梨県甲府盆地の西部を流れる御勅使川(みだいがわ)は、富士川水系に属する一級河川で、この川は山地から大量の土砂を運び、その中には砂や礫(れき)が多く含まれていました。
現在では流路が固定されていますが、その以前には扇状地で洪水が発生すると扇状地上を自由に乱流してしまい耕地も洪水のたびに破壊されてしまう様相だったようです。また同時に、礫質土壌のため透水性が高く、水がすぐに地中へ浸透してしまうため、農業用水の確保が非常に困難でした。
そこで考え出されたのが、用水路から扇状地へ水を引くための分水口と、それを守るための工夫です。
御勅使川扇状地に用水を引くために分水口を設ける必要があり、分水口を洪水から守るために築かれたのが桝形堤防です。そして、この桝形堤防と耕地を守るために「将棋頭(しょうぎがしら)」と呼ばれる三角錐型の堤防が設けられ、洪水が発生した場合にも耕地や民地を守るように作られています。
これらは1700年ごろ作られたと考えられており、この二つの構造物は、先人たちの知恵と技術を示す貴重な遺構として、現在では史跡整備が行われ国指定文化財となっています。
これらの堤防や水路の工夫によって、御勅使川扇状地では水田が増え、地域社会に大きな変化がもたらされたと考えられています。
300年前も土木技術が暮らしを豊かにし地域の発展を支えたこと、また治水と利水の歴史が現在に繋がっていることが分かる史跡だと感じました。
参考・出展
山梨県 南アルプス市HP|史跡御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出) 史跡整備完成・および一般公開開始!
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/16388.html
南アルプス市ふるさとメール: 桝形堤防史跡整備の歩みその1~水の世紀を生きる道標~
https://sannichi.lekumo.biz/minamialps/2022/09/post-72a5.html