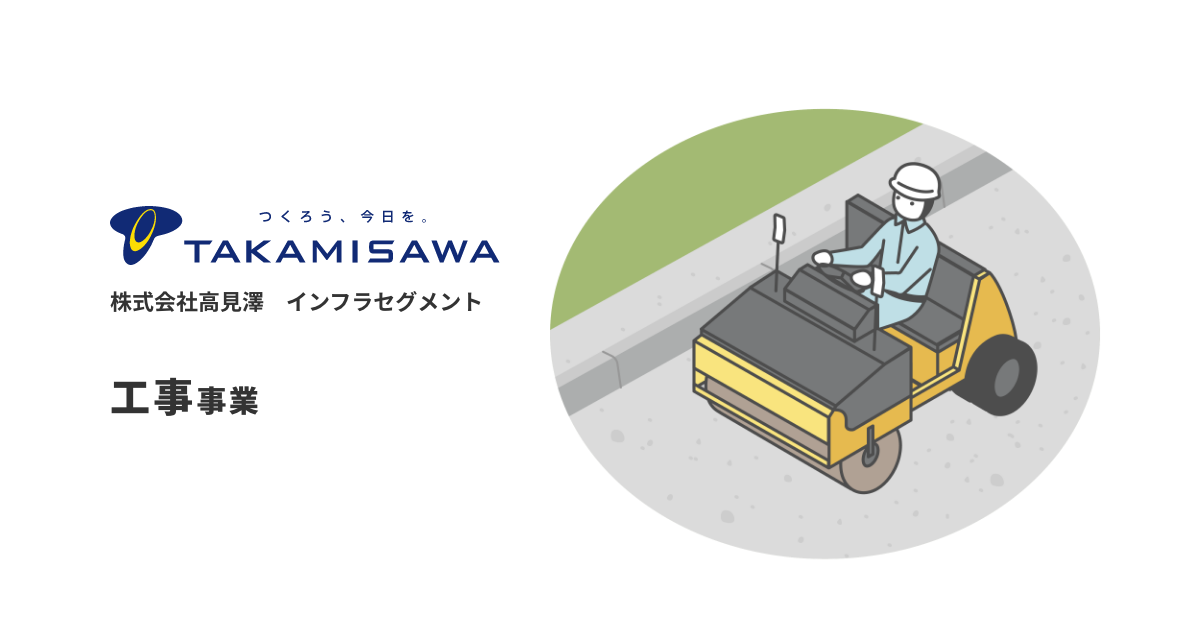土木工事
土木工事とは
土木工事は、暮らしを支える社会インフラづくりの要です。
工事の種類ややりがい、3K(=きつい・きたない・危険)払拭への取り組みを通じて、土木の魅力をわかりやすく紹介します。
社会を支える縁の下の力持ち
土木工事と聞いて思い浮かべるのは何でしょうか?家やビルを作る工事は建築業と呼ばれ、建築基準法などの法律に則り工事が行われます。一方、土木工事というと道路やダム、橋などのインフラ設備のことを指すのが一般的です。
道路法や河川法といった法律の他、道路橋示方書や道路土工指針(出版:公益社団法人 日本道路協会)といった技術基準書がまとめられています。土木工事はビルを作るような目立つ仕事ではありませんが、皆様の安心・安全そして快適に暮らせるインフラ作りをする仕事です。まさに【縁の下の力持ち】と言えるでしょう。

土木工事の種類
土木工事の中にも様々な種類があり、一部を紹介します。
1. 道路工事(舗装、歩道整備、交差点改良)
新しく道路を作るだけでなく、道路の拡幅や、歩道・自転車道の新設工事があります。
また道路舗装は経年劣化で痛んでいってしまうため定期的な修繕工事が必要となります。
2. 橋梁工事(橋の新設、耐震補強、修繕)
橋を新しくかける工事の他、昔に作られた橋の修繕や耐震補強をする工事です。
近年では築造後50年以上経過した橋が増加してきており、特に橋の点検・補修が重要となってきています。
平成26年に国土交通省「道路橋定期点検要領」が試行され、5年に1回の頻度での点検を基本とし、その健全性については4段階に区分することとされました。
3. 河川・治水工事(堤防建設、護岸工事、河川改修)
河川の堤防、護岸を整備する工事です。
特に令和元年東日本台風(台風第19号)の災害では広い範囲で河川の氾濫・浸水害、土砂災害等の甚大な被害が発生したことを受け、国は”国土強靭化”を打ち出し、今まで以上に河川の堤防強化・治水対策への取り組みが進められています。
4. 上下水道工事(配管敷設、メンテナンス)
新規の上下水道整備の他、こちらも老朽化がすすむ施設(管路)の点検・修繕が重要となっています。
5. 港湾・海岸工事(防波堤、岸壁整備)
東日本大震災の教訓を踏まえ、粘り強い構造の防波堤整備が進められています。
また、四方を海に囲まれた日本において港湾整備は人や物の流通拠点として非常に重要です。
国土交通省では港湾の中長期政策「PORT 2030」と位置づけ、物流・エネルギー資源の受入・供給体制の整備などが進められています。(URL参照)
3Kを払拭するために
皆様は工事現場にどのようなイメージがあるでしょうか?
かつて土木業界は「3K:きつい、きたない、危険」と言われていました。
しかし、少子高齢化や働き方の変化により、土木業界も変革が求められ、「安全性」「快適性」「効率性」を高める技術導入や職場環境の改善が進みつつあります。
1. ICT施工の導入
ICT施工(Information and Communication Technology 施工)とは、情報通信技術を活用して 土木工事を効率化・高度化する取り組みです。簡単に言うと、”デジタル技術で現場をスマートにする” 取り組みです。 ドローンやレーザーを使った3D測量、3 次元モデルを活用したBIM、CIM。遠隔操作や自動制御ができる重機を使用し作業員の負担低減などが行われています。
2. 女性・若者が働きやすい環境整備
綺麗な現場事務所や更衣室を導入することや、仮設トイレの様式化・水洗化などが行われています。
3. 働き方改革
働き方改革の一環として週休2日制の導入が進められています。
工期や工程の見直しの他、資料作成などのバックオフィスを充実させることで現場の負担軽減に取り組んでいます。
また、発注者の取り組みとして年度末に集中しがちだった工事発注のタイミングを年間を通して均等に行うなど官民一体となって環境改善が図られています。
4. 安全の見える化
現場の安全を守るため ”見える化” が非常に重要です。事故ゼロ日数、注意喚起などの掲示板の設置やヒヤリハットの共有などの従来の取り組みに加え近年ではセンサーやカメラを活用し危険エリアへ進入した場合にアラートが発出する仕組みなど活用されています。
5. イメージ改善
未来の担い手を育てるために若者に土木の魅力を伝える取り組みが行われています。
高校などの教育機関と連携し、工事現場を見学したりインターンシップの受け入れを行い、働く職場のリアルな雰囲気や、土木の役割ややりがいを感じてもらい、業界のイメージアップに取り組んでいます。
社会の役に立つ仕事

建設業に関わる方々からは、「やりがいを感じる」という声が多く聞かれます。
その背景には、土木の仕事が「縁の下の力持ち」として、道路や橋、上下水道などのインフラ整備を通じて人々の暮らしを支えているという実感があります。
また、災害時には誰よりも早く現場に入り、復旧作業に取り組むことで、地域の命と生活を守るという使命感もやりがいにつながっています。
さらに、公園や緑地の整備などを通じて、自然と共存する街づくりに貢献し、地域の景観や憩いの場を創出する役割も担っています。
こうした仕事は、目に見える形で社会に残るため、完成したときの達成感は格別です。
人々の生活を支え、未来の街をつくる――そんな誇りと責任を持って働けることこそが、土木の魅力であり、最大のやりがいであると言えるでしょう。