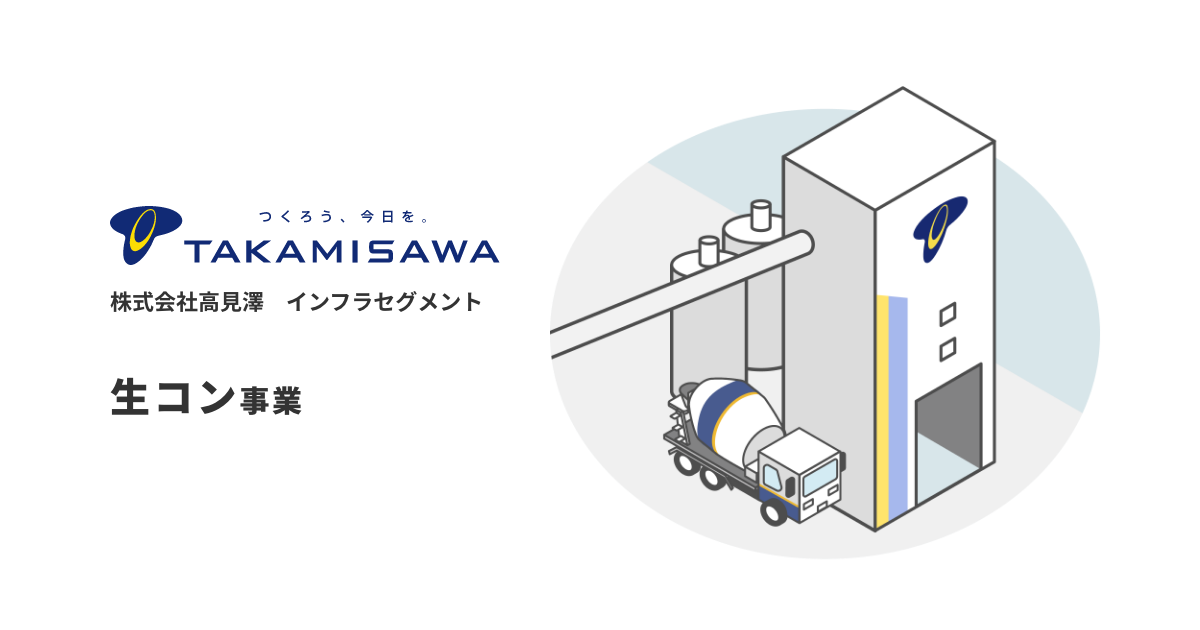生コンクリート
セメントペースト
石灰系の粉末であるセメントと練り水を均一になるよう練り混ぜたものをセメントペーストと呼びます。セメントペーストは水と接した瞬間から反応が始まるため均一の品質にはなりづらく、JIS規格(日本産業規格)などで定められた規格や基準がありません。
用途:セメントペーストは直接構造体として使用することは少なく、隙間充填剤や地盤改良、既成杭の周辺固定液としての活用が一般的です。
モルタル
セメントと水、細骨材(砂)を練り混ぜた材料がモルタルです。モルタルもセメントペーストと同様に規格などは存在しません。
用途:目地材や接着剤、補修材、等様々な用途で使用されています。
コンクリート
コンクリートとはセメントと水、細骨材(砂)、粗骨材(砂利)、を練混ぜて一体化した材料のことです。コンクリートはJIS規格などをもとに、必要とする強度や流動性、耐久性、施工性などを考慮し配合設計します。また、練混ぜ方法や練混ぜ時間もJIS規格をもとに定められています。
主要な構成材料はセメント、水、骨材ですが、この他必要に応じて混和剤や空気が配合されます。
コンクリートの種類と製造規定
生コンの製造について、JIS規格(JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)に規定があります。
1. 普通コンクリート
呼び強度18~45(N/mm2)までのコンクリート
2. 高強度コンクリート
普通コンクリートよりも強度が高いコンクリート(呼び強度60(N/mm2)以上)
強度が高い分、部材断面を小さくすることができるため、建築分野では居住空間を広くとることができます。
3. 軽量コンクリート
骨材の全部または一部に人工軽量骨材を用いて、普通コンクリートよりも軽量化したコンクリート
4. 舗装コンクリート
曲げ強度を基準とし、すりへり抵抗性や疲労抵抗性が高い等,舗装に適したコンクリート
この他、施工条件などにより様々なコンクリートが工事に使われています。
- 気温による条件(寒中・暑中コンクリート)
- 大型構造物や高層ビルなどの条件(マスコンクリート・高流動コンクリート)
- 施工場所による条件(水中コンクリート・海洋コンクリート)
コンクリートの構造と特徴
鉄筋コンクリート(RC造)
コンクリートと鉄筋が一体となって外力に抵抗する構造です。コンクリートは ”圧縮力に強い、引張力に弱い” という特徴があり、コンクリートの強度と言うと一般に圧縮強度(押される力に対する強さ)を指します。

コンクリートの引張り強度は圧縮強度の1/10程度と非常に小さいため、引張り強度の大きい鉄筋がコンクリートの引張強度を補強するために用いられています。
また、鉄筋が補強材として用いられる理由にコンクリートとの相性の良さがあります。
物質は温度によって伸び縮みしますが、コンクリートと鉄筋は熱膨張係数がほぼ同じなため一体となって働くことができます。また、鉄筋はサビに弱いですが、コンクリート中の強アルカリ環境下ではサビが生じづらくなり、加えてコンクリートに包まれることで耐火性も向上します。
このように鉄筋とコンクリートはお互いの弱点を補強しあっています。

鉄筋コンクリート構造は下記に示したように、建築・土木などで幅広く使用されています。
主な用途
- 住宅・オフィスなど小~中規模一般建築の柱梁・壁・床版・基礎
- 小~中規模橋梁、道路や護岸、水路といった土木構造物 など
長所
- 設計自由度が高く、耐震・耐火・耐久・遮音性能に優れる
- 現場打ち・プレキャストとも量産体制が確立している
短所
- 自重が大きく長スパンでは部材断面や自重がネック
- 鉄筋腐食(塩害・中性化)対策が不可欠
- 型枠・養生など工程が多く工期が長い
無筋コンクリート
引張力がほとんど生じない、またはその影響を考慮しない場合には、コンクリート単体で構成される無筋コンクリートが使用されます。
鉄筋がないため、前出の通り、圧縮には強いが、曲げ・引張・せん断に対しては弱い構造です。
主な用途
- 重力式擁壁・ダム・大断面基礎など
- 「マスコンクリート」と呼ばれる大容量打込みで、自己重量で安定を図る構造が多い
長所
- 鉄筋を使用しないため型枠内にコンクリートを充填しやすい
- コストが安い
- 腐食部材が無い
短所
- 使用できる構造物が限定的
- 部材断面が大きくなりがち
プレストレストコンクリート(PC造)
プレストレストコンクリートとPC鋼材を緊張(引っ張る)させて、あらかじめ圧縮応力(プレストレス)を生じさせることで曲げひび割れに対する耐力を向上させたコンクリートです。
コンクリートへのプレストレス(圧縮応力)の導入はPC鋼材と呼ばれる高強度の鋼材を使います。
PC鋼材を両側から引っ張って緊張させた状態でコンクリートと固定させます。
すると両側から引っ張られたPC鋼材には縮もうとする力が生じ、同時にコンクリートにも圧縮応力が生じることになります。

プレストレストコンクリートは導入方法によりプレテンション方式とポストテンション方式に大別されます。
プレ(pre=事前に)テンション方式
PC鋼材を緊張させたところにコンクリートを打設し、定着させます。主にプレキャストコンクリートで採用されます。
ポスト(post=後に)テンション方式
コンクリート硬化後にPC鋼材を緊張させ、定着させます。コンクリート打設時にPC鋼材を通す穴(シース)を設け、PC鋼材は定着具によって定着させます。主に現場でのプレストレス導入に採用されます。
主な用途
- 長スパン橋梁(PC桁橋・斜張橋・箱桁橋)、高速道路高架、タンク・サイロ・煙突、PC床版、床梁の無柱大空間、免震PC杭 など
長所
- ひび割れが抑制され耐久性が向上
- スリムで軽量 → 支間40~100 m の長スパン/大荷重に対応
- 変形性能・振動性能が良い(たわみ制御)
短所
- 初期コストが高い
- 設計が高度
- 完成後の孔あき・切断など改修が難しい
- PC鋼材腐食が進行すると健全性に大きな影響
コンクリートの施工(鉄筋コンクリート)

コンクリート工事の流れ
1. 鉄筋工事
RC造の場合、設計図に基づいて鉄筋を組立てます。鋼材は熱を加えると粘り強さが失われるなど劣化が生じてしまうため原則熱を加えない方法で加工されます。
2. 型枠工事
生コンクリートは合板(ベニヤ板)などを用いて組立てた型枠内に流し込み、コンクリートの硬化後型枠を取り外します。型枠さえ用意できれば、比較的自由に造形できるのがコンクリート構造物の特徴の一つです。型枠工事や寸法精度の他、生コンから型枠にかかる側圧などを考慮し組み立てる必要があります。
3. コンクリート打設
運搬
所定の品質に基づき、生コン工場から建設現場へ運搬します。運搬はトラックアジテータかダンプトラックが使用されます。トラックアジテータは一般的にミキサー車、生コン車と呼ばれ後部にドラム式の攪拌機を搭載した車です。運搬中もコンクリートを攪拌し固まらないように、また、品質が保たれるようになっています。
 運搬時間はJIS A 5308の規定により、"生コン工場で練り混ぜ開始後から現場の荷下ろし地点に到着するまで1.5時間以内とする"とされています。(ダンプトラックの場合1時間以内)
運搬時間はJIS A 5308の規定により、"生コン工場で練り混ぜ開始後から現場の荷下ろし地点に到着するまで1.5時間以内とする"とされています。(ダンプトラックの場合1時間以内)
生コンは建設現場で荷下ろしの際、受入検査を行います。強度やスランプ(生コンの柔らかさ)空気量、塩化物含有量を検査し品質を確認します。
打設
受入れ検査に合格した生コンはコンクリートポンプ、コンクリートバケット、ベルトコンベヤなどを用いて、型枠内に打設します。
- コンクリートポンプ
生コンを高圧で配管を通し、打設場所まで送る車両のこと

コンクリートポンプの圧送方法と仕組み
|
圧送方法
|
仕組み
|
特徴
|
|---|---|---|
|
ピストン式 |
シリンダー内でピストンを前後に動かすことでコンクリートの吸いこみと圧送を連続して行います。水鉄砲のようなイメージです。 |
|
|
スクイズ式 |
ゴム製のチューブをローラーで押しつぶしながらコンクリートを押し出す方法です。チューブ容器(歯磨き粉など)のイメージです。 |
|
- コンクリートバケット
コンクリートバケットは、クレーンなどで吊り上げて生コンクリートを運搬・打設するための容器です。ポンプ車での圧送が難しい現場や、少量打設、複雑な型枠といった様々な現場で使用される。
仕組み:ミキサー車から生コンクリートをバケットに流し込み、クレーンでバケットを吊り上げ、打設箇所まで移動・打設を行います。
特長:クレーンで移動するため振動が少なく、材料分離が生じにくい。機材が比較的シンプルでコストが抑えられる。
4. 締固めと仕上げ
ドロドロとしたコンクリートをしっかりと型枠内にいきわたらせるために、振動機(バイブレーター)を使って締固めます。振動を与えすぎると材料分離が生じてしまうため、コンクリートが材料分離せず、また大きな空隙ができないように締め固めることが重要です。振動機を使用できない場所では型枠を木づちで叩き、コンクリートを付き棒でついて締固めます。
コンクリートの打ち込み終了後、型枠に面していない箇所の表面を仕上げます。
一般的な工程
- 粗削り(大まかに合わせて均す)
↓ - 定規ずり(長い定規で表面を平らにする)
↓ - こて仕上げ(木ごてや金ごてを使って表面を平滑に仕上げる)
5. 養生
コンクリートが固まるまで、コンクリートを保護することを「養生」と呼びます。コンクリートは水分と反応して硬化するため、乾燥や温度変化に注意する必要があります。
養生期間は「建築工事標準仕様書」によると、標準使用期間で5日以上とされており、この他、使用するセメントの種類や、計画耐用年数ごとに設定されています。