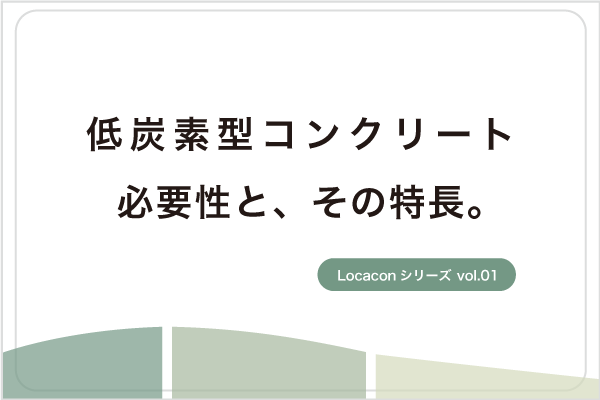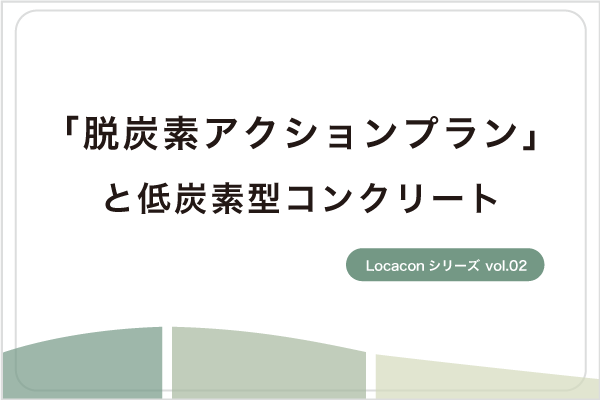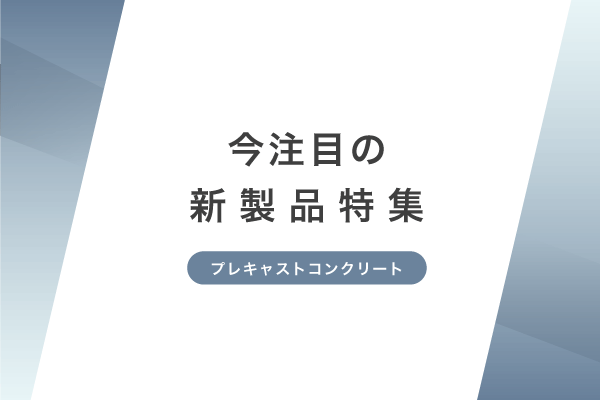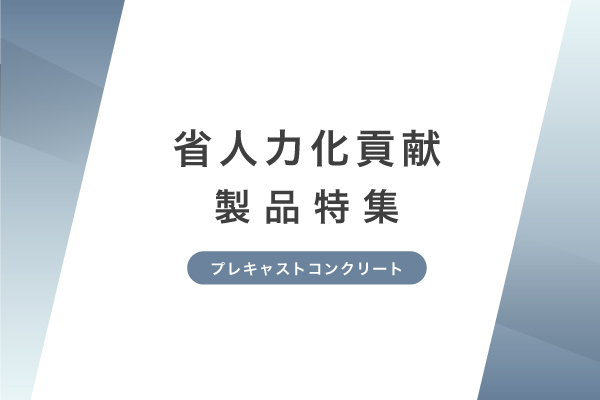近年、建設現場で話題を集めているのが「低炭素型コンクリート」です。
国土交通省の脱炭素アクションプランを追い風に、全国の公共工事でもいよいよ本格導入が進み始めています。
コンクリートとCO2の関係
私たちの身の回りにある建物、道路、橋などの社会インフラの多くは、コンクリートによって支えられています。
しかし、この身近な建設材料が実は地球温暖化の大きな要因の一つとなっていることをご存知でしょうか。
コンクリートの主要原料であるセメントの製造過程では、大量のCO2が排出されますが主に2つの要因に分けられます。
①化学的プロセスによる排出
一つ目は、原料である石灰石(炭酸カルシウム:CaCO3)を焼成する際の脱炭酸反応による排出です。石灰石を約900℃以上で加熱すると、
CaCO3 → CaO + CO2という化学反応が起こり、この過程で必然的にCO2が発生します。
②燃料燃焼による排出
二つ目は、焼成に必要な高温(約1,450℃)を維持するための燃料燃焼による排出です。この燃焼過程でもCO2が発生します。
化学プロセス、燃料燃焼によるCO2排出の全体では、セメント1トンの製造には約0.8~1.0トンのCO2排出を伴うとされており
その約60%が化学的プロセス、約40%が燃料燃焼に起因します。
日本のセメント産業のCO2排出量は、年間約4000万t。これは、日本の総CO2排出量の約4%、産業部門の第4位となります。出典1
このような背景から、従来のコンクリートに代わる「低炭素型コンクリート」の開発と普及が、環境問題解決の重要な鍵として注目されています。
低炭素型コンクリートとは?
低炭素型コンクリートとは、従来のポルトランドセメントの一部を産業副産物などの代替材料で置き換えることにより、セメント使用量を低減したコンクリート製品です。これによりセメント由来のCO2を大幅に削減できます。
代替材料には高炉スラグ、フライアッシュ、シリカフュームなどがあり、環境負荷の軽減を図りながら、性能面でも従来品と同等以上の品質を確保します。
これらの代替材料の中でも広く用いられている高炉スラグ微粉末を配合したコンクリート製品の特長を下記にまとめました。
- 長い年月でさらに強くなる
通常のコンクリートよりも、時間が経つほど強度が増加します。 - アルカリ骨材反応の抑制
コンクリート内部で起こる有害な化学反応(アルカリ骨材反応)を抑え、ひび割れや劣化を防ぎます - 化学抵抗性 向上
酸や塩分などの化学物質に強くなり、海水や薬品によるコンクリートの劣化を防ぎます - 凍結融解抵抗性の向上
凍結融解とは、寒さによりコンクリート内部の水分が膨張・収縮することでコンクリートの劣化が生じる現象です。
高炉スラグ微粉末を配合したコンクリートで凍結融解抵抗性が高くなり、寒冷地でもコンクリートが壊れにくくなります。
このように高炉スラグを用いることで、CO2排出を抑制できるだけでなくコンクリートの機能・耐久性が向上します。
ライフサイクルコストの低減にもつながります。
高炉スラグはコンクリート用スラグ骨材として利用され始めたのは今からなんと100年近く前の1900年代初頭。出典2,3
また1977年にはJIS規格として制定されました。
このように高炉スラグ微粉末は、コンクリート用骨材として古くから使われており、コンクリートの性能を高める効果が広く知られています。
低炭素型コンクリート「Locacon」
高見澤が製造する流し込み製品は全て低炭素型コンクリート「Locacon」です。

低炭素型コンクリート「Locacon」は、コンクリート中に使用するセメントを製鉄所から排出される高炉スラグ微粉末で置き換え、セメント使用量を減らすことでCO₂排出量の大幅な削減を実現しました。
セメント置換率は、前述された国土交通省の指標55%を大きく上回る最大60%です。

これにより従来の全てセメントで製造する製品と比較しCO2が58%削減できます。
具体的な例として当社の道路用L型擁壁「ハイパーロードL型」H1000Aを100m施工した場合のCO2削減量を試算した場合
約2,400kgのCO2が削減できます。

これはマイカー通勤2年間やめた場合のCO2量相当となるため、非常に大きな削減効果が見込めます。
<Locaconの詳細情報はこちらから>
まとめ
ここでは低炭素型コンクリートの必要性や、その特徴を簡単にまとめました。
その2では国土交通省の「脱炭素アクションプラン」を取り上げ、低炭素型コンクリートをとりまく市況を解説します!
参考・出展
出典1:国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス編 環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室監修 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書(2022年)日本の温室効果ガス排出量データ(1990~2020年度)確報値
https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html
出典2:鐵鋼スラグ利用のあゆみ|鉄鋼スラグ製品に関する調査・研究、普及活動|鐵鋼スラグ協会
https://www.slg.jp/association/history/
出典3:公益社団法人 日本コンクリート工学会 月刊コンクリート技術「2022年12月号」
https://www.jci-net.or.jp/j/concrete/technology/202212_article_1.html